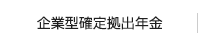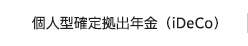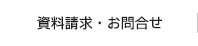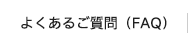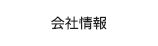た行
た
第1号被保険者 Category 1 insured persons
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生などのことです。
第2号被保険者 Category 2 insured persons
国民年金の加入者のうち、厚生年金保険の被保険者(会社員、公務員、私立学校の教職員)のことです。(老齢年金の受給権を有する65歳以上の者は除く。)
第3号被保険者 Category 3 insured persons
20歳以上60歳未満で、第2号被保険者(会社員、公務員、私立学校の教職員)に扶養されている配偶者のことです。
退職一時金 Lump-sum distribution of retirement benefits
従業員が定年や自己都合などで退職する際に、一時金として受け取る資産のことです。退職一時金には、税制優遇措置(退職所得控除)があります。
退職給付債務(PBO) Projected Benefit Obligation
退職金や年金として将来給付すべき債務の現在価値のことです。2000年4月1日より導入された新会計基準においては、退職給付債務に積立不足がある場合は退職給付引当金として企業のバランスシート上に負債として計上しなくてはならなくなりました。
退職所得控除 Deduction from retirement income
退職金にかかる税金を計算する際、課税所得から控除される金額のことです。
ターゲット・デート(ターゲット・イヤー)型 Target Date (Target Year)
バランス型投資信託のひとつで、資産配分が時間の経過により変動します。退職を迎える日をターゲット・デートと想定し、時間の経過とともに資産配分を自動的に変更します。一般に年齢が上がるとリスク許容度は低くなるため、徐々にリスクを抑えた資産配分に変更します。一般的に、ターゲット・デートの異なる複数の商品(コース)が用意されており、年数の経過とともに商品(コース)追加がおこなわれます。ターゲット・イヤー型と呼ばれることもあります。
脱退一時金 Early lump sum distribution
確定拠出年金では、所定の要件を満たした場合に限り、個人別管理資産を受け取ることができます。脱退一時金は通常の一時所得とみなされ、所得税および住民税が課税されます。
単位型投資信託 Unit investment trust
投資信託の分類の一つで、当初募集期間だけ買い付けが可能で、設定後は買い付けできないタイプの投資信託のことをいいます。
短期金融資産 Short-term financial assets
金融機関や法人専用の確定金利の金融商品のことです。コールローン、譲渡性預金(CD)などがあり、期間は1日から3ヶ月程度のものが一般的です。
ち
中小企業退職金共済(中退共) Smaller enterprise retirement allowance mutual aide
1959年に制定された中小企業退職金共済法に基づいて、中小企業を対象に、従業員福祉の充実と雇用の安定を図るために設けられた退職金制度のことです。中退共と略されます。
中小事業主掛金納付制度 Contribution payment plan for small and medium-sized companies
中小事業主掛金とは、個人型年金において、加入者の掛金に上乗せして企業が拠出する掛金のことで、法令の要件を満たした事業主が国民年金基金連合会に届け出ることで実施することができます。
中途解約利率 Cancellation rate
預金商品などの満期がある商品で、満期を待たずに途中で換金した場合に適用される利率のことです。
つ
追加型投資信託 Open type stock investment trust
投資信託の分類の一つで、当初募集・設定された後、時価で追加購入ができるタイプの投資信託のことです。
通算加入者等期間 Total participation period
60歳までの企業型年金加入者期間、企業型年金運用指図者期間、個人型年金加入者期間、および個人型運用指図者期間を通算した期間のことです。また、他の企業年金等からの移換金や制度移行金があった場合は、その金額の算出の根拠となった加入期間も通算します。
通算拠出期間 Total contribution period
企業型年金および個人型年金に掛金が払い込まれた期間の合算のことです。 また、他の企業年金等からの移換金や制度移行金があった場合は、その金額の算出の根拠となった期間も通算します。
て
DC(ディーシー) DC
Defined Contributionの略で確定拠出年金のことです。
定性評価 Qualitative analysis
ファンドの評価方法の1つで定量的な分析だけでは把握することができない運用方針、運用プロセスなどをファンドアナリストが直接運用会社、ファンドマネージャーにヒアリング等をして評価をすることです。
DB(ディービー) DB
Defined Benefitの略で確定給付型年金のことです。
定量評価 Quantitative analysis
ファンドの評価方法の1つで過去のパフォーマンス(運用成果)など数値的なもので評価することです。また株価などの評価においても、企業の財務諸表や株価収益率等の数値を基に分析することを定量分析といいます。
と
投資信託 Investment trust
複数の投資家の資金を一つにまとめて基金を作り、専門家(委託会社)が株式や債券などの有価証券等に分散投資をする仕組みの金融商品のことです。投資信託自体も有価証券の一種で、投資家は投資信託という有価証券の持ち主となり、専門家が運用した利益、損失ともに持ち分に応じて分配される仕組みになっています。「投信」と略したり、「ファンド」と言うこともあります。証券会社、保険会社、銀行などの金融機関で販売されており、株式、債券に投資するもの、外国の資産に投資するもの、取引所に上場しているもの等様々な投資信託商品があります。
特定期間 Instruction Period
指定運用方法を提示している企業型年金の加入者となり、最初に事業主掛金等の納付が行われた日から起算して、3ヶ月以上で年金規約で定める期間のこと。当該期間中、運用の指図(配分割合の指定)が行われていなければ、記録関連運営管理機関から加入者に通知します。(関連用語:指定運用方法、みなし指図、猶予期間)
特別法人税 Special corporate tax
企業年金の積立金に対して課せられる税金のことをいいます。ただし、現在課税は凍結されています。
TOPIX(東証株価指数) TOPIX (Tokyo Stock Price Index)
東京証券取引所が日々発表している国内株式の代表的な指標です。1968年1月4日の時価総額を100とし、その後の時価総額を指数化したものです。
トップダウン・アプローチ Top-down approach
投資信託における個別銘柄選定において、まず、経済・金融情勢、景気動向等の調査に基づいて国別配分や業種別配分を決め、それから個別銘柄の選定を行っていく手法のことです。
ドル・コスト平均法 Dollar cost averaging
同一の銘柄を一定の金額で定期的に継続して購入する投資手法のことです。購入する金額を一定にすると、価格が高い時には数量は少なく、価格が低い時には数量を多く購入することになり、購入コストの平準化が可能となります。この方法は株式や投資信託等を積立方式で購入する場合に効果的と言われています。